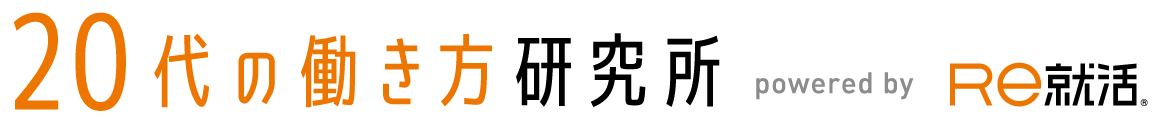2025.04.09INTERVIEW
「すべての人に一輪の花を」ITxメンタルヘルスで、社会課題解決のため、大学生で起業。挑戦を続けるキャリアに迫る

アトラスト・ヘルス株式会社
代表取締役社長
バローチ・ニール様
厚生労働省によれば、生涯を通じて、5人に1人はこころの病にかかると言われています。こころの病気は特別ではなく、誰でもかかりうるもの。現在、約428万人が精神疾患を患っています。また、2016年発行の世界精神保健調査によれば日本の精神疾患の障害有病率は22.9%であり、実に約2,900万人が疾患を患う可能性があります。その一方、精神医療へのアクセスは未だに高いハードルがあると、今回お話を伺ったバローチさんは言います。ITを活用し、精神医療システムの効率を上げ、医療業界と精神疾患を患う患者個人をサポートするアトラスト・ヘルス社を立ち上げたバローチさんは、なぜ精神医療というテーマにアプローチするのか。そして、どんな社会を実現したいのかをインタビューしました。
バローチさんは高校生の時に起業に興味を持ち始め、スニーカー愛好家の向けのプラットフォームを作りました。そこから、より根本的な社会課題にコミットするため、精神医療に特化した事業を展開するアトラスト・ヘルス社を大学生の頃に立ち上げました。
アトラスト・ヘルス株式会社の「オンライン×対面の総合精神医療プラットフォーム『WeMeet』」
同社は24時間365日対応の精神医療に特化した総合精神医療プラットフォーム「WeMeet」を開発・提供しています。プラットフォーム上で対面診療とオンライン診療を選択可能。オンライン診療の場合は、予約から受診、決済、お薬や書類の受け取りまでをオンラインで完結することができ、医療機関への受診ハードルを下げるとともに、早期のうちに精神科・心療内科系疾患の発見に繋げることが期待されるサービスです。
―大学生の時に起業されたと伺いました。昔から起業をしたいと考えていたのでしょうか
そもそも、父親が自営業だったこともあり、会社員としてのキャリアの歩み方が自分の中では一般的ではありませんでした。そんな中で、高校の授業の一環で経営者の方からお話を聞く機会があり、イキイキと自分の会社について話す姿が印象的だったんです。そして、大学では商学部に進学し、マーケティングを専攻しました。学術的な研究ではなくて、もっと実践的な経験を積みたいと考えていました。
―「スニーカー愛好家向けのプラットフォーム」を、大学1年次に立ち上げられたと聞いています
当時は自分の手でプロダクトを生み出したいという思いを持っていました。何を手がけようか考えた時に、スニーカーが好きだったこともあって立ち上げに至りました。
スニーカーの愛好家が、情報交換や購入・販売するのをサポートするオンラインサイトで、出品されるスニーカーはきちんと鑑定書がついているものだけになるような仕組みも設けていました。有名ブランドやプレミアのついているものにはニセモノも多数流通してしまっています。1人のスニーカー愛好者として安心して取引できる場を作ってみたかったんです。
また、オンラインプラットフォームをつくるためにエンジニアやデザイナーの知識も身に付けようとしていました。将来的に何か大きな事業を成し遂げるためには、それだけ多くの仲間が必要ですし、多少なりとも仲間に担ってもらう領域について分かっておかなければならないと感じました。
―そして大学3年次にはアトラスト・ヘルス株式会社を立ち上げられました。大きな方針転換だなと感じます
より大きな課題にチャレンジしたいと考えたことがきっかけです。課題が大きいほど、解決した時にはより大きな感動やインパクトを届けられると思いました。精神疾患は5大疾病の一つで、年間400万人近い患者さんがいます。こうした状況を改善するためのプレーヤーは存在するものの、まだまだ多くはありません。そこに自分もトライしたいと考えました。
―なぜ精神疾患の課題に挑戦したいと考えたのでしょう
中学校時代の友人の影響が大きいです。彼はうつ病で通院していたのですが、本人から打ち明けてもらうまでは、そのことに全く気づきませんでした。早い段階で医療にアクセスできたため重篤化を防ぐことはできていたようですが、通院している様子を見ると受診までのハードルは高いものだと思ったのです。
―ハードルが高いとは具体的にどのようなことでしょうか
一つは物理的なハードルです。近くに精神科の病院はあるものの、予約がとれなくて遠くの病院で受診するしかないという状況がありました。遠くの病院になるほど、通院も大変です。また、心理的なハードルもありました。地元のコミュニティは小さく、精神科に通院しているところを見られてしまうと悪い噂を立てられてしまうかもしれません。それに中学生同士なら、まだ社会も十分に知らないので、きっとその友人にネガティブな印象を持ってしまったり、ある種の負の烙印のようなものを押してしまうかもしれません。
現在は精神疾患に関する社会的な認知度は高まってきていますが、それでもこうした状況は大きく変わっていないと思います。
―中学生時代の体験が大きなきっかけになったのですね
起業をするときに、向き合うべき課題は何なのか自分自身を振り返りました。その時、この中学生時代の体験が自分の中では大きなものでしたし、友人にどのように接したら良いのかインターネットでたくさん調べたことも思い出しました。

2019年に当社を立ち上げ、多くの投資家に事業への支援を打診しましたが、良い反応ばかりではありませんでした。どなたも立ち向かうべき課題であることは認識してくれるものの、ビジネスとして成り立つ可能性が乏しいと思われてしまいました。断られた投資家の数も3桁に上ります。
それでも、毎年、数十万人もの困っている人がいるわけで、この課題には何としてでも取り組まなければと考えていました。
―諦めるという選択はなかったのでしょうか
病気を患ったとしても、きちんと医療にアクセスし社会復帰をして、より豊かな生活を送ってほしいという思いが根底にはありましたから、諦めようとは思いませんでした。一方で、自分の思いだけを伝えても賛同が得られにくいのは当たり前です。投資家はどんな情報を求めていて、何を指標としているのか今一度考えなおし、利益をきちんと生み出せるビジネスモデルであることや、市場規模の大きさなどを丁寧に伝えていきました。そして、少しずつではありますが賛同いただける方が増えていったのです。
―精神医療を取り巻く環境を変えていくことが一番の目的なら、起業以外にも医療業界への就職といった選択もあったのではないでしょうか
既存のプレーヤーに属するのではなく、新しい仕組みでこの業界を変えるくらいのインパクトを生み出したかったので、起業にはこだわっていました。当初は小さく事業を展開していましたが、徐々にスケールを大きくすることに成功しています。
諸外国のスタートアップの成功事例を見ると、20代といった若手よりもシニア世代の起業の方がうまくいっています。これまで培ってきたノウハウや人脈を生かした経営が出来ているからです。一方で、20代には行動力という強みもあります。
そこで当社もベテランのメンバーに参画してもらい事業を成長させています。2019年創業ながら平均年齢は35歳。代表の私が一番若いという会社なので、行動力を発揮しつつ、メンバーの様々な知見を吸収し前に進むことができています。
そもそも私は組織で仕事する経験をしていません。会社とはどのように運営されるものであるのか、採用や社員の定着のためにはどうすればいいのかなど、経営するにあたって大きな会社を経験しているメンバーは大変貴重だと思っています。

人類の健康寿命を延ばしたいといった思いはもちろんあるのですが、患者さんにだけフォーカスしてしまうと医療業界の慣習と折り合いがつかなくなってしまうかもしれませんし、方や、医療業界にだけ目を向けていては患者さんを置き去りにしてしまうかもしれません。ですから業界と患者さん両方に寄与しつつ、橋渡しになるような存在になりたいと考えました。
一人ひとりの患者さんにはそれぞれ背景や課題があって、その課題一つ一つに向き合って解決を図っていく丁寧なアプローチをしていきたいと思っています。また、「精神科」や「心療内科」という言葉を聞くだけでも、人によっては一昔前の精神病院を想起してしまうこともあり、ネガティブな印象は残り続けています。私たちの取り組みによって、そうした精神医療のリブランディングのようなことができないかとも考えています。
日本の医療品質は世界的に見ても高水準で、かつ比較的安価に受診できます。こうした医療環境にはしっかりと敬意を払いつつ、何かプラスアルファでできることを模索しているというわけです。
―「人類」という言葉を使われていることも印象的です
精神疾患にまつわる課題はなにも日本だけのことではありません。当然、各国で医療システムは異なるので、それぞれに合ったアプローチ方法は考えなければなりませんが、広く精神医療の課題を解決するという目的のもと、いつかは海外にもサービスを展開することを視野に入れて事業に取り組んでいきたいと考えています。
―そうした課題に対して、どのようにアプローチしていきたいと考えているのでしょうか
医療機関での体験をより良いものにしたいというのが私たちの事業の目的の一つです。例えば通院にあたって待ち時間が長いことなど負担が大きいのが現状です。それに、どの医療機関や医師が良いのかも人によって異なります。私たちのサービスを通じてより良い患者体験を実現していきたいです。
現在も、サービス利用者のデータを収集・分析して医療体験を向上させており、少しずつではありますが、より医療へのアクセスもオープンなものになっていると感じています。
―そんな貴社のこれからの展望や目標についてお聞かせください
ビジョンに「すべての人に、“一輪の花”を。」と掲げています。これはある患者さんの体験に基づいて考えました。その人は精神疾患を患い、これまで出来ていたことが少しずつ出来なくなっていってしまいました。毎日、これからどうしようと不安であったと言います。
そんな中、心療内科を受診し、良い医師と巡り合うことができ、治療を通じて少しずつ元の生活に戻っていった経験があったと聞いています。主治医は服薬だけでなく、趣味の読書を、焦らず、少しずつで良いから始めてみましょうと、自身の状況に合わせて親身にアドバイスしてくれたそうです。その患者は、症状が回復したとき、いつかは自分の本屋さんを開きたいという夢まで語ってくれました。
このエピソードから、精神医療の環境を変えていくことで、患者さんが自分の幸せを再発見し、人生をより豊かなものにすることができるのではないか、そして私たちの事業を通じて実現したい最終的な目標もここにあるのではないかと考えました。患者さん一人ひとりが大きな不安を抱えていますが、“一輪の花”がある、すなわち幸せが見つかる世界なんだということを伝えていきたいのです。
疾患を抱えた患者さんが一足飛びに状況を良くすることはできないかもしれませんが、少しずつでも前に進んでいき、最終的に病気を乗り越えてこれまでよりも希望にあふれた人生を歩むきっかけづくりをしていきたいと考えています。
―お話いただいたように、医師との相性も治療においては大きなポイントだと思います。サービスの開発・改修もあわせて行っていくのでしょうか
はい。医師の人柄なども含めてマッチングできるようにしていきたいと考えています。これまでの精神医療では病院に行って初めて医師と出会うようになっていました。ですが、一人ひとりの医師の考え方やスタンスは異なっており、受診前からそのスタンスを可視化することでより良いマッチングを図れるようにしていきたいと思っています。また、医師の顔写真なども登録していき、色々な情報で自分に適した診療を受けられるようにしていきたいですね。
―ここまでお話いただきありがとうございました。最後にこれからのキャリアを考える読者へのメッセージをお願いします
まず、今のシステムが必ずしも最適ではないかもしれないという視点でアンテナを張ることだと思います。それと同時に、いま無いものは過去に誰かがチャレンジしたけれどできなかったのかもしれない。そして、そのできなかった背景には何があるのかということに目を向けることも大切です。その人はなぜうまくいかなかったのかを探るということですね。この二つを意識していくと、自ずとやりたい事や、進むべき道筋が見えてくるようになると思います。
私たちの事業は、精神医療へのアクセスのハードルを下げ、より良い医療体験を提供していくというもので、重篤化する前に受診できるようにするという観点では予防医療的な側面があります。
日本でも予防医療にトライする会社は多いものの、例えばアメリカと比較すると市場規模は小さいものです。なぜなら、日本は医療費が安いので、体調が少しでも悪ければ簡単に医療にアクセスできるからです。かたや、アメリカは医療費が高い。医療機関に通う頻度を少なくするために予防医療が大切になっていきます。
ですが、そんな日本でも特に精神医療分野ではそもそもの受診ハードルが高く、また周囲からの見られ方も気にしなければならない現状です。ほかの疾病や怪我と同じように気軽に病院にアクセスすることが重要ですが、まだまだ改善の余地があります。なぜそれが出来ないのか、実現するためのハードルが何か、過去に同じような取り組みをした人がいないのか、そうしたことを調べて、私たちはいまサービスを提供しているのです。結果として事業成長のスピードを高めつつ、失敗率も下げることが出来ているのではないかなと感じています。


アトラスト・ヘルス株式会社
2019年7月12日設立。オンライン×対面の総合精神医療プラットフォーム事業と、クリニックDX支援サービス事業を展開。精神医療、メンタルヘルスケアのアクセシビリティの向上・医療体験の向上を通じ、広く人類が自らの生を肯定できる世界の創出を目指す。2024年5月には同社の成長が評価されシリーズAラウンドでの資金調達を完了している。
代表取締役社長
バローチ・ニール様
厚生労働省によれば、生涯を通じて、5人に1人はこころの病にかかると言われています。こころの病気は特別ではなく、誰でもかかりうるもの。現在、約428万人が精神疾患を患っています。また、2016年発行の世界精神保健調査によれば日本の精神疾患の障害有病率は22.9%であり、実に約2,900万人が疾患を患う可能性があります。その一方、精神医療へのアクセスは未だに高いハードルがあると、今回お話を伺ったバローチさんは言います。ITを活用し、精神医療システムの効率を上げ、医療業界と精神疾患を患う患者個人をサポートするアトラスト・ヘルス社を立ち上げたバローチさんは、なぜ精神医療というテーマにアプローチするのか。そして、どんな社会を実現したいのかをインタビューしました。
バローチさんは高校生の時に起業に興味を持ち始め、スニーカー愛好家の向けのプラットフォームを作りました。そこから、より根本的な社会課題にコミットするため、精神医療に特化した事業を展開するアトラスト・ヘルス社を大学生の頃に立ち上げました。
アトラスト・ヘルス株式会社の「オンライン×対面の総合精神医療プラットフォーム『WeMeet』」
同社は24時間365日対応の精神医療に特化した総合精神医療プラットフォーム「WeMeet」を開発・提供しています。プラットフォーム上で対面診療とオンライン診療を選択可能。オンライン診療の場合は、予約から受診、決済、お薬や書類の受け取りまでをオンラインで完結することができ、医療機関への受診ハードルを下げるとともに、早期のうちに精神科・心療内科系疾患の発見に繋げることが期待されるサービスです。
在学中に起業。中学校時代の体験が原点に
―大学生の時に起業されたと伺いました。昔から起業をしたいと考えていたのでしょうかそもそも、父親が自営業だったこともあり、会社員としてのキャリアの歩み方が自分の中では一般的ではありませんでした。そんな中で、高校の授業の一環で経営者の方からお話を聞く機会があり、イキイキと自分の会社について話す姿が印象的だったんです。そして、大学では商学部に進学し、マーケティングを専攻しました。学術的な研究ではなくて、もっと実践的な経験を積みたいと考えていました。
―「スニーカー愛好家向けのプラットフォーム」を、大学1年次に立ち上げられたと聞いています
当時は自分の手でプロダクトを生み出したいという思いを持っていました。何を手がけようか考えた時に、スニーカーが好きだったこともあって立ち上げに至りました。
スニーカーの愛好家が、情報交換や購入・販売するのをサポートするオンラインサイトで、出品されるスニーカーはきちんと鑑定書がついているものだけになるような仕組みも設けていました。有名ブランドやプレミアのついているものにはニセモノも多数流通してしまっています。1人のスニーカー愛好者として安心して取引できる場を作ってみたかったんです。
また、オンラインプラットフォームをつくるためにエンジニアやデザイナーの知識も身に付けようとしていました。将来的に何か大きな事業を成し遂げるためには、それだけ多くの仲間が必要ですし、多少なりとも仲間に担ってもらう領域について分かっておかなければならないと感じました。
―そして大学3年次にはアトラスト・ヘルス株式会社を立ち上げられました。大きな方針転換だなと感じます
より大きな課題にチャレンジしたいと考えたことがきっかけです。課題が大きいほど、解決した時にはより大きな感動やインパクトを届けられると思いました。精神疾患は5大疾病の一つで、年間400万人近い患者さんがいます。こうした状況を改善するためのプレーヤーは存在するものの、まだまだ多くはありません。そこに自分もトライしたいと考えました。
―なぜ精神疾患の課題に挑戦したいと考えたのでしょう
中学校時代の友人の影響が大きいです。彼はうつ病で通院していたのですが、本人から打ち明けてもらうまでは、そのことに全く気づきませんでした。早い段階で医療にアクセスできたため重篤化を防ぐことはできていたようですが、通院している様子を見ると受診までのハードルは高いものだと思ったのです。
―ハードルが高いとは具体的にどのようなことでしょうか
一つは物理的なハードルです。近くに精神科の病院はあるものの、予約がとれなくて遠くの病院で受診するしかないという状況がありました。遠くの病院になるほど、通院も大変です。また、心理的なハードルもありました。地元のコミュニティは小さく、精神科に通院しているところを見られてしまうと悪い噂を立てられてしまうかもしれません。それに中学生同士なら、まだ社会も十分に知らないので、きっとその友人にネガティブな印象を持ってしまったり、ある種の負の烙印のようなものを押してしまうかもしれません。
現在は精神疾患に関する社会的な認知度は高まってきていますが、それでもこうした状況は大きく変わっていないと思います。
―中学生時代の体験が大きなきっかけになったのですね
起業をするときに、向き合うべき課題は何なのか自分自身を振り返りました。その時、この中学生時代の体験が自分の中では大きなものでしたし、友人にどのように接したら良いのかインターネットでたくさん調べたことも思い出しました。

既存のプレーヤー任せではなく、自ら新しいシステムを生み出したい
―大きな課題に向き合うという志を持ちつつ、一方でビジネスとしても成立させないといけないと思います。難しさがあったのではないでしょうか2019年に当社を立ち上げ、多くの投資家に事業への支援を打診しましたが、良い反応ばかりではありませんでした。どなたも立ち向かうべき課題であることは認識してくれるものの、ビジネスとして成り立つ可能性が乏しいと思われてしまいました。断られた投資家の数も3桁に上ります。
それでも、毎年、数十万人もの困っている人がいるわけで、この課題には何としてでも取り組まなければと考えていました。
―諦めるという選択はなかったのでしょうか
病気を患ったとしても、きちんと医療にアクセスし社会復帰をして、より豊かな生活を送ってほしいという思いが根底にはありましたから、諦めようとは思いませんでした。一方で、自分の思いだけを伝えても賛同が得られにくいのは当たり前です。投資家はどんな情報を求めていて、何を指標としているのか今一度考えなおし、利益をきちんと生み出せるビジネスモデルであることや、市場規模の大きさなどを丁寧に伝えていきました。そして、少しずつではありますが賛同いただける方が増えていったのです。
―精神医療を取り巻く環境を変えていくことが一番の目的なら、起業以外にも医療業界への就職といった選択もあったのではないでしょうか
既存のプレーヤーに属するのではなく、新しい仕組みでこの業界を変えるくらいのインパクトを生み出したかったので、起業にはこだわっていました。当初は小さく事業を展開していましたが、徐々にスケールを大きくすることに成功しています。
諸外国のスタートアップの成功事例を見ると、20代といった若手よりもシニア世代の起業の方がうまくいっています。これまで培ってきたノウハウや人脈を生かした経営が出来ているからです。一方で、20代には行動力という強みもあります。
そこで当社もベテランのメンバーに参画してもらい事業を成長させています。2019年創業ながら平均年齢は35歳。代表の私が一番若いという会社なので、行動力を発揮しつつ、メンバーの様々な知見を吸収し前に進むことができています。
そもそも私は組織で仕事する経験をしていません。会社とはどのように運営されるものであるのか、採用や社員の定着のためにはどうすればいいのかなど、経営するにあたって大きな会社を経験しているメンバーは大変貴重だと思っています。

より良い医療体験を通じ、より豊かな人生を実現させる
―ミッションとして「医療業界へのコミット」と「人類へのコミット」を掲げられています。この二つをミッションとしたのはどのような背景からなのでしょうか人類の健康寿命を延ばしたいといった思いはもちろんあるのですが、患者さんにだけフォーカスしてしまうと医療業界の慣習と折り合いがつかなくなってしまうかもしれませんし、方や、医療業界にだけ目を向けていては患者さんを置き去りにしてしまうかもしれません。ですから業界と患者さん両方に寄与しつつ、橋渡しになるような存在になりたいと考えました。
一人ひとりの患者さんにはそれぞれ背景や課題があって、その課題一つ一つに向き合って解決を図っていく丁寧なアプローチをしていきたいと思っています。また、「精神科」や「心療内科」という言葉を聞くだけでも、人によっては一昔前の精神病院を想起してしまうこともあり、ネガティブな印象は残り続けています。私たちの取り組みによって、そうした精神医療のリブランディングのようなことができないかとも考えています。
日本の医療品質は世界的に見ても高水準で、かつ比較的安価に受診できます。こうした医療環境にはしっかりと敬意を払いつつ、何かプラスアルファでできることを模索しているというわけです。
―「人類」という言葉を使われていることも印象的です
精神疾患にまつわる課題はなにも日本だけのことではありません。当然、各国で医療システムは異なるので、それぞれに合ったアプローチ方法は考えなければなりませんが、広く精神医療の課題を解決するという目的のもと、いつかは海外にもサービスを展開することを視野に入れて事業に取り組んでいきたいと考えています。
―そうした課題に対して、どのようにアプローチしていきたいと考えているのでしょうか
医療機関での体験をより良いものにしたいというのが私たちの事業の目的の一つです。例えば通院にあたって待ち時間が長いことなど負担が大きいのが現状です。それに、どの医療機関や医師が良いのかも人によって異なります。私たちのサービスを通じてより良い患者体験を実現していきたいです。
現在も、サービス利用者のデータを収集・分析して医療体験を向上させており、少しずつではありますが、より医療へのアクセスもオープンなものになっていると感じています。
―そんな貴社のこれからの展望や目標についてお聞かせください
ビジョンに「すべての人に、“一輪の花”を。」と掲げています。これはある患者さんの体験に基づいて考えました。その人は精神疾患を患い、これまで出来ていたことが少しずつ出来なくなっていってしまいました。毎日、これからどうしようと不安であったと言います。
そんな中、心療内科を受診し、良い医師と巡り合うことができ、治療を通じて少しずつ元の生活に戻っていった経験があったと聞いています。主治医は服薬だけでなく、趣味の読書を、焦らず、少しずつで良いから始めてみましょうと、自身の状況に合わせて親身にアドバイスしてくれたそうです。その患者は、症状が回復したとき、いつかは自分の本屋さんを開きたいという夢まで語ってくれました。
このエピソードから、精神医療の環境を変えていくことで、患者さんが自分の幸せを再発見し、人生をより豊かなものにすることができるのではないか、そして私たちの事業を通じて実現したい最終的な目標もここにあるのではないかと考えました。患者さん一人ひとりが大きな不安を抱えていますが、“一輪の花”がある、すなわち幸せが見つかる世界なんだということを伝えていきたいのです。
疾患を抱えた患者さんが一足飛びに状況を良くすることはできないかもしれませんが、少しずつでも前に進んでいき、最終的に病気を乗り越えてこれまでよりも希望にあふれた人生を歩むきっかけづくりをしていきたいと考えています。
―お話いただいたように、医師との相性も治療においては大きなポイントだと思います。サービスの開発・改修もあわせて行っていくのでしょうか
はい。医師の人柄なども含めてマッチングできるようにしていきたいと考えています。これまでの精神医療では病院に行って初めて医師と出会うようになっていました。ですが、一人ひとりの医師の考え方やスタンスは異なっており、受診前からそのスタンスを可視化することでより良いマッチングを図れるようにしていきたいと思っています。また、医師の顔写真なども登録していき、色々な情報で自分に適した診療を受けられるようにしていきたいですね。
―ここまでお話いただきありがとうございました。最後にこれからのキャリアを考える読者へのメッセージをお願いします
まず、今のシステムが必ずしも最適ではないかもしれないという視点でアンテナを張ることだと思います。それと同時に、いま無いものは過去に誰かがチャレンジしたけれどできなかったのかもしれない。そして、そのできなかった背景には何があるのかということに目を向けることも大切です。その人はなぜうまくいかなかったのかを探るということですね。この二つを意識していくと、自ずとやりたい事や、進むべき道筋が見えてくるようになると思います。
私たちの事業は、精神医療へのアクセスのハードルを下げ、より良い医療体験を提供していくというもので、重篤化する前に受診できるようにするという観点では予防医療的な側面があります。
日本でも予防医療にトライする会社は多いものの、例えばアメリカと比較すると市場規模は小さいものです。なぜなら、日本は医療費が安いので、体調が少しでも悪ければ簡単に医療にアクセスできるからです。かたや、アメリカは医療費が高い。医療機関に通う頻度を少なくするために予防医療が大切になっていきます。
ですが、そんな日本でも特に精神医療分野ではそもそもの受診ハードルが高く、また周囲からの見られ方も気にしなければならない現状です。ほかの疾病や怪我と同じように気軽に病院にアクセスすることが重要ですが、まだまだ改善の余地があります。なぜそれが出来ないのか、実現するためのハードルが何か、過去に同じような取り組みをした人がいないのか、そうしたことを調べて、私たちはいまサービスを提供しているのです。結果として事業成長のスピードを高めつつ、失敗率も下げることが出来ているのではないかなと感じています。


アトラスト・ヘルス株式会社
2019年7月12日設立。オンライン×対面の総合精神医療プラットフォーム事業と、クリニックDX支援サービス事業を展開。精神医療、メンタルヘルスケアのアクセシビリティの向上・医療体験の向上を通じ、広く人類が自らの生を肯定できる世界の創出を目指す。2024年5月には同社の成長が評価されシリーズAラウンドでの資金調達を完了している。