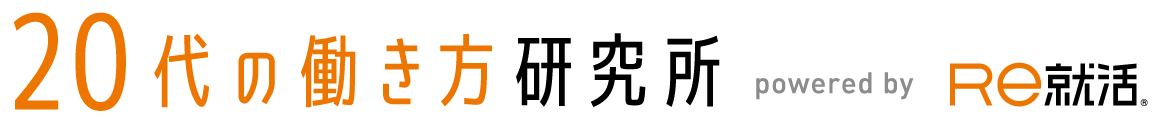最近話題の「治療用アプリ」ってなに?MIT卒業後、MICINで事業開発を行いながら目指す「すべての人が納得して生きる」世界とは。
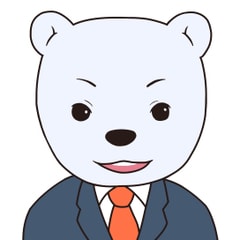 20代の働き方研究所 研究員 T.I.
20代の働き方研究所 研究員 T.I.
デジタルセラピューティクス事業部
國尾 美絵(くにお みえ)様
「治療用アプリ」をご存じでしょうか?今回お話を伺ったのは、株式会社MICIN(マイシン)でこの「治療用アプリ」の開発を行う國尾さん。中学時代の経験から地域の医療格差に関心を寄せ、工学的なアプローチで医療を支えるために慶應義塾大学理工学部に入学。修士課程中には医学の知識が必要だと考え、修士修了後にMIT(マサチューセッツ工科大学)に留学し、医療工学を学んでPh.D.を取得されました。その後はアメリカで大手精密機器メーカーキャノン(Canon U.S.A. Inc.)にて医療機器の研究開発に従事。「事業開発」に携わりたいという気持ちが芽生えたことから、帰国後には実現したい世界のビジョンが同じであったマイシンに入社して、「治療用アプリ」の開発チームで活躍されています。「治療用アプリ」によってどのように世界が変わっていくのか、そして自らが感じた社会課題の解決にアプローチするにはどんな方法をとればいいのか、國尾さんのお考えを伺いました。
【治療用アプリとは】
医師によって患者に処方されるアプリ。患者はアプリをダウンロードして使用することで、疾患への対処方法が分かったり、健康状態の記録、それに基づくアドバイスなどを受け取ることができ、アプリを通じて治療を受けることができます。次世代の医療の在り方の一つとして注目されています。
「治療用アプリ」で治療に新たな選択肢を
―次世代の医療として「治療用アプリ」を手掛けられていますが、コロナ禍でオンラインでの診療や処方など、医療のオンライン化も進んでいます。医療の在り方が変わりつつありますねいままでは医師の診療を受けるには自分が病院に行かなければならないという固定観念がありましたが、コロナ禍を経て必ずしも対面で受診する必要はないのでは?という意識に変わってきました。これは就活における選考や説明会がオンラインでもできることに世の中が気づいた感覚に似ていますね。
また、コロナ以前から、病院から遠いところに住む患者さんは通院が難しいという社会課題もあったので、コロナ禍を皮切りにここ数年でオンライン診療は増えてきました。それでも、日本は欧米に比べて少し遅れています。
日本でも誰もがスマホを持っている、常にオンラインで繋がっている時代です。オンライン診療だけでなく、もっと治療にもスマホを活かして医療を充実させるために、症状に合わせて医師から薬のように処方される「治療用アプリ」というものもここ数年で生まれています。
私はマイシンでこの「治療用アプリ」を研究・開発しています。ただ、いままでオンラインによる診療が一般的ではなかった状況に加え、「治療用アプリ」も一般的ではない中で全国に普及させるには、社会的な信用を得たり、アプリを理解してもらう必要があります。研究・開発だけでなく「治療用アプリ」を広めていく仕事も私の業務のひとつです。
―「治療用アプリ」とはどんなものでしょうか
医療でアプリを活用するというと、医師とオンラインで話すことができるとか、治療の記録が残る、みたいなイメージかと思いますが、「治療用アプリ」はそこから一歩先にいった製品です。
風邪に罹ったから医師から風邪薬をもらう、といったように、病気や症状に合わせたアプリを薬のように医師から処方してもらい、患者さんは家で使って治療効果を出す、というものが「治療用アプリ」です。
現在マイシンでは、ストレスがかかるとお腹が痛くなってしまう「過敏性腸症候群」に対して、認知行動療法を活用して治療を行うアプリの開発に向けた研究を行っています。
また、治療生活を支援するアプリとして、手術を受ける患者さんを主なターゲットに「MedBridge(メドブリッジ)」も展開しています。手術前には疾患について詳しい知識がなかったり、生存率を過度に気にしてナイーブになってしまったり、医師からたくさんの説明を受けてパンクしてしまったりと、大きな不安を抱えてしまうものです。「MedBridge」はこれを解消するために、自身の疾患についての知識を配信したり、入退院に向けてどのような準備が必要なのかを理解してもらうツールとして、また自分自身の治療記録を付けてもらうツールとしてお使いいただいています。
―DTx(デジタルセラピューティクス)の分野は、業界全体としても開拓途中な領域ですよね
おっしゃる通りで、みんなが手探りです。ただ、開拓途中だからこその面白さを味わえる分野でもあります。新しい世界を拓いていくというのはものすごく大変なことですが、誰かが取り組まないと医療も発展しません。また、医療分野は保守的になりやすい領域です。そんな中でどうやってDTxを広めていくのか、どうやって新しいものを生み出し、取り入れることで医療を良くしていけるのか、という点に面白さを感じていますし、やりがいを感じています。
※DTx(デジタルセラピューティクス):明確な定義はありませんが、患者のスマホにアプリをインストールして治療に役立てるなど、デジタル技術で疾患の予防や診断・治療するソフトウェアなどを指します。歩数の計測やダイエットを目的としたアプリは既に存在しますが、それらとは一線を画し、エビデンスや薬事承認が必要で、治療介入を目的として医師の管理下でのみ処方されます。

医療の地域格差を解決するための進路選択
―國尾さんがこうした次世代の医療に関心を持ったきっかけを教えていただけますか中学生の頃、親戚が田舎に住んでいたのですが、医療へのアクセスは都市部よりも限定的で、オンライン診療などが身近なものでもありませんでした。治療を受けるにはちょっと離れた都市部にある病院へ行かざるを得ない。でも体力がないから遠出ができず、都市部では普通に受けられる医療を受けることができない、という状況だったのです。
親戚が亡くなった時、別の親戚から「都市部に住んでいれば助かったのかもしれない」という話を聞き、医療の地域格差というものを目の当たりにしました。当時の悔しさが、「医療をどうにかしたい」という思いのベースとなっています。
誰もが最終的には死んでしまう世界において、医療は患者さんが最後まで納得して生きるための手段です。その医療が、地域によって受けられるものに差があるという現実にどうしても納得ができなかったのです。
―医師を目指すという選択はとらなかったのでしょうか
「医師にならないの?」とはよく言われていました(笑)。ただ、医師は患者さんが治らない病気だったとしても、その事実を伝えなければならないですよね。患者さんが死に向かっているという現実と向き合い続けることは並大抵のことではありません。私にはその覚悟がなく、医師を目指す選択はとりませんでした。
その後、あるテレビ番組で介護ロボットを見たことがきっかけで、工学的な分野から医療に関わっていく選択肢を見出しました。当時はロボット技術が発達してダヴィンチ手術なども出てきましたし、考えてみれば手術室にはいろんなデバイスがありますよね。こうしたデバイスも誰かが研究し、作り上げたものです。この気づきから工学的なアプローチで医療に関わっていくことを決めました。
―そのビジョンを実現するために、慶應義塾大学の理工学部へと進学されたんですね
元々医療工学を志してはいたのですが、医療工学の中でもどういった方向に進むかは決めあぐねていました。一方で当時の私は化学が苦手で、生物もそこまで得意ではなく、なんで医療工学を選んだんだと思われても仕方がない状況でした(笑)。ただ、数学や物理は得意だったので、医療工学の中でも薬学のような化学の領域ではなく、物理の領域で何かできないかと考えていました。
慶應義塾大学の理工学部には、学門制という制度があります。これは一年生の時には学科を決めず、いくつかの学科を統合した5つの学門の中から選択して入学し、二年生への進級時に自身の学科を選択し、専門性を身につけていくという制度です。
私は専門性を身につける前に、もっと広く知識を得たいと考えていたので、自分にマッチしている、かつ医学部があり、医工連携の取り組みも数多くあるという点に魅力を感じ、この選択をしました。
―そこからさらに、MITへと学びの場を展開されたと伺いました
慶應義塾大学には修士まで在籍しました。医工連携の取り組みも多いですし、医療工学の取り組みももちろんたくさんあったので、非常に有意義な期間であったと感じています。しかし、もっと学びを深めるためには、医師と同水準の医学の知識を身につける必要があると考えるようになりました。
当時、医学部生は工学について学ぶことができる一方で、理工学部生が医学を学ぶチャンスは非常に限られており、医工連携について学びつつ、医学についても学ぶ方法を探していました。
そんな中、たまたま学会でボストンへ行く機会があり、そこでMIT時代の指導教官と出会いました。その先生が教える学部は、医工連携はもちろん、医学生が学ぶ基本的な内容をすべて学べるカリキュラムが組まれており、私にとっては願ったり叶ったりの環境です。すぐにMITへ行くにはどうすればいいのか、調べ始めました。
―自分のビジョンを実現するためとはいえ、留学という選択をすることに、ためらいはなかったのでしょうか
ありましたよ、ものすごくありました(笑)。すでに慶應で博士課程へ進学することが決まっていましたし、当時は実家暮らしだったので、初めての1人暮らしが海外になるという勉強の面だけではない不安も抱えながらの決断でした。
とはいえ両親が応援してくれたのも大きな後押しとなりました。それに幼少期から引っ込み思案だったのですが、この留学への一歩が、引っ込み思案を克服するきっかけにもなりましたね。
入学試験では、まず書類選考があり、定員の倍数ほどまで絞り込まれます。そして面接があるのですが、対面かオンラインか選択可能なところ、自分の思いをしっかりと伝えるために現地を選びました。三日間ぐらいのスケジュールでしたが、日中の面接が終わったその夜には一緒にディナーを食べながらお話しましょう、みたいな場面もあって衝撃を受けました(笑)。
ネイティブが話す英語のスピードは当然ですがとても速く、ボストンのなまりもあるのでコミュニケーションに苦労しましたが、伝えたいことが漏れないようにプレゼン資料のようなものを紙ベースで持っていき、自分の思いをぶつけました。いまでも当時の面接官から、「資料まで作ってきたのは後にも先にもお前しかいない、そこまでがんばっているやつを見たことがない」と言われます。

アメリカの「研究開発職」から日本の「事業開発職」へ
―そうした学びの経験を経て、ファーストキャリアにはアメリカの医療機器を扱う企業の研究開発職を選ばれています。その選択にはどんな理由があったのでしょうかこれまでも一貫して医療分野について学習していたので、医療業界であるというのは外せませんでした。あとはせっかくPh.D.まで取ったので最初は研究開発職がいいとも考えていました。自分のやりたいことを実現できうる環境であれば、アメリカでも日本でも特にこだわりはなかったです。
その中でもアメリカのキャノンに入社を決めた理由としては、当時、医療部門を立ち上げて1、2年ほどで、新しい挑戦が受け入れられる環境であったことが挙げられます。また、それまで自分が取り組んでいた研究が直接的に活かせる分野であったこと、そしてキャノンは言わずと知れた世界トップレベルの画像処理技術を持っていることに魅力を感じ、入社を決めました。
私は医療機器の中でも画像診断の分野で研究開発に取り組みました。製品化に向けては大型動物を使った実験など、様々な工程を踏まなければなりませんが、医療部門を立ち上げて間もなくの会社です。製品化のステップについても自分たちできちんと定義づけしていく必要がありました。また、組織が拡大していくにつれて挑戦できることも増えていき、多くの経験を積むことができたと思っています。それまではアカデミックな研究ばかり行ってきたので、製品化につなげるための研究開発や組織づくりというものについて知ることができたというのは大きな財産になりました。とりわけ医療の分野には規制やルールがたくさんあります。その枠組みの中で、どのようにして製品化までこぎつけるかを常に考えることは、自分にとって大きな成長の機会となりました。
―そして現在ではマイシンで事業開発職としてご活躍されています。自ら事業開発に携わりたいと考えたきっかけを教えてください
自分が研究開発職としてキャノンに入った時、決められたプロジェクトに対してこれまでの自分の研究をどう活かすかを一番に考えていました。しかしながら、どれだけ研究を活かせたとしても、また技術が進歩したとしても、製品をローンチするまでにはたくさんの壁があって、なんでこんなに壁にぶち当たるんだろう、と悩むことが多々ありました。
また、そもそも自分の取り組んでいるプロジェクトを、原点である医療格差の解決につなげるにはどうしたらいいのか考えることもありました。それならば、自ら事業を開発し、より直接的に課題解決に取り組もうと思ったのです。
私がマイシンを選んだ理由としては、マイシンが掲げる「すべての人が、納得して生きて、最期を迎えられる世界を。」というビジョンが、私のやりたいことにマッチしていたことが一番の理由です。
アメリカの「研究開発職」から日本の「事業開発職」へ転職したわけですが、研究開発も「こうすれば課題が解決するはずだ」と仮説を立て、検証をしていくという点において、事業開発と類似しています。検証して世の中に製品を出すところまで担うのが事業開発という違いこそあれ、フレームワークは変わっていません。これまでの経験も活かせる環境であるというのも魅力でしたね。
―マイシンのビジョンにある「納得して生きる」とはどういうことなんでしょうか
みんなが幸せに、とか、みんなにより良い医療を、みたいな話ではなく、あくまで「納得して」なんですよね。この「納得」というのは究極の個人化だと考えていて、私が納得する治療法と誰かの納得する治療法は違います。少しでも苦しまない最期を迎えられる治療法なのか、苦しんででも一秒でも長く生き続ける治療法なのかなど、様々な選択肢がある中で、誰もが納得できる治療法をちゃんと選んで、その治療に対して後悔なく生きていける、というのがマイシンの目指す世界なのです。
そして私の目指す世界は「自身の身近な人たちが最期まで笑っている世界」です。笑うことや幸せでいることは、いまの自分の環境を自分自身で選んだという納得感があってはじめて実現できることだと思います。マイシンのビジョンを実現することで私の目指す世界も実現するので、このビジョンを実現するために仕事に取り組んでいきたいと考えています。
まずはオンライン医療や治療用アプリを用いた医療の地域格差のない世界の実現から。みんなが求める医療が同じレベルで手に入る世界を目指していきたいと思います。

日常で感じるちょっとした「引っ掛かり」を解決するために
―「医療の地域格差をなくす」という一貫した課題意識を軸に持ちつつ、学習の場や課題解決へのアプローチは常にアップデートされていることが印象的です。そのためにはどんなことが必要でしょうか?
社会生活の中で、誰しも言語化されていないなにかしらの「引っ掛かり」を感じることがあると思います。ちょっとした不便を感じたり、慣れてしまって気づかなかったけど、ふとした瞬間にあれ?となるようなこともあると思います。
そういった「引っ掛かり」が言語化される瞬間を仕事の中で感じることが多いです。課題を解決するために事業を開発する、研究と検証を行う中で、それが「引っ掛かり」にピタッと当てはまると、課題と解決までの道のりが見えてきます。それが第一歩です。
もう一点、仕事にしっかりと取組み、成果を出し続けることも、アプローチをアップデートしていく上で助けになります。成果を出し続けるというのは、基礎的ですが大変なことですよね。それをきちんとやることで、周りも見ていてくれますし、新しいことを任せてみようと考えてくれます。國尾だったらやってほしい、とか、國尾に任せたらどうにかなるんじゃないかと周りの方々にも思ってもらうことで、自分では思いつかなかったような新たなアプローチを実践する機会に恵まれるのです。
―ここまでありがとうございました。最後に、20代の読者へメッセージをお願いします
私は心配が先に立つ人間で、「こんなことできないかも」という不安にいつも苛まれています。そんな中でもやってみた、という経験は大きな価値になります。次に不安に襲われたときも、積み重ねた経験が私の背中を押してくれます。
また、私は早い段階で「医療に携わりたい」という目的を見つけることができましたが、目的を見つけるのに遅すぎるということはありません。「これめちゃくちゃたのしい!」とか「この課題を解決したい!」という出会いがあったのなら、まずは今自分がやっている仕事にどう活かせるかから考えてみてもいいかもしれませんね。

株式会社MICIN
2015年11月設立。
「すべての人が、納得して生きて、最期を迎えられる世界を。」をビジョンとして掲げ、テクノロジーの力で医療の可能性を拡げていく事業を展開。2023年4月には大腸がん、肺がん患者向けの周術期管理アプリを用いた探索的臨床研究を開始するなど、人生の最期に「こんなはずじゃなかった」と思う人をなくすために邁進している。