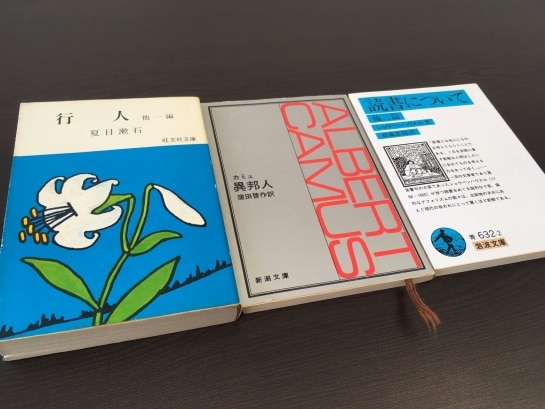
趣味は読書なんですけど、そう言ったら十中八九「何の本が好きなの?」と聞かれますが、その答えって、案外センスを求められるんですよね。
あんまり王道な作品を答えるとコノ雑魚ガって顔されるし、マニアックすぎる作品だとチベットスナギツネみたいな顔にさせちゃう。
だから、今回はいい感じに“読書好き”をアピールできる本を、独断と偏見で選んでみました。
夏目漱石『行人』
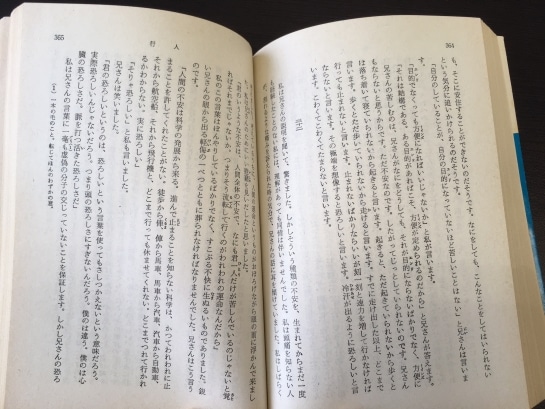
誰もが知ってる作家の王道すぎない作品っていうのは、相手もイメージしやすいし「そんな本も書いてるんだ~」って食いつきがいい。
この話は簡単に言うと学問馬鹿な兄・一郎が思考の泥沼にはまって孤独にもがいて愛する妻も信じられず弟・二郎2人で泊まってこいと自ら寝とられ展開に持っていく、って内容なんですが、まあとにかく一郎兄さんに共感できすぎるんですよ。
「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入るか。僕の前途にはこの3つのものしかない」
人生を真面目に生き過ぎて、真理を追い求めすぎて、気が付かなければ楽に生きれたのに気が付いてしまったから苦しんで。
普通に生活をしてても現実感がないというか、何もしたくないのに何かせずにはいられないというか、何かちゃうねん!こうじゃないねん!というか。
一郎兄さんの台詞でとくにグサッと刺さったのがこの言葉。
「自分のしていることが自分の目的になっていないほど苦しいことはない」
ああ!この閉塞感。たまらんね。
じゃあ自分の目的って何か?そもそも人間の目的って何か?って考え始めると、命を食べて子孫作って命をつなぐ、ってことになる。なんだそりゃ。
経験から言いますけど、考えない方が幸せに生きれるんですよ。諦念ですよ。で、楽しい、嬉しい、って思うことに、素直に忠実になることが大事なんだなと最近は思うようになりましたね。
カミュ『異邦人』
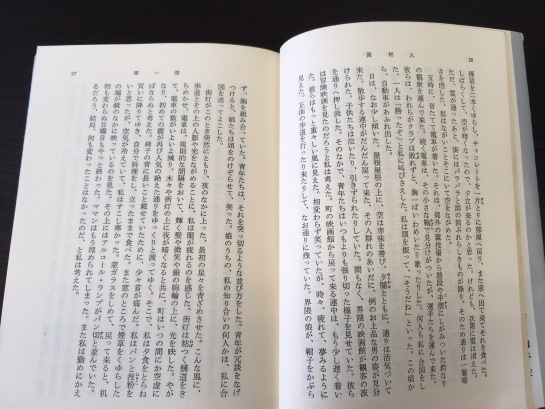
聞いたことあるけど読んだことはない海外作品、ってのも興味を持ってもらいやすいです。
「きょう、ママンが死んだ」の書き出しではじまるこの話は、ママンが死んだ翌日に海で遊んで女の子といちゃいちゃして映画を見て笑い転げて“太陽がまぶしかったから”人を殺して死刑判決を受けて刑務所の神父の説教にブチぎれて死刑までの唯一の希望は処刑の日に見物人に憎悪の叫びをあげて迎えられることだ、って内容なんですが、こう書くと碌でもないやつだ、ムルソーくん。
でも、全編通して読むと主人公・ムルソーの、発生するそれぞれの事象に対して素直に反応するスタンスっていうのは好感がもてるし共感もできるんですよ。
母の死は悲しいけど、長らく離れて暮らしていたし明日からも変わらない日常が続くんだろうと思う。嫌われ者のご近所さんも自分にとって悪い奴じゃないから楽しく話す。判事の質問にも思ったことを正直に答える。
「みんなそうしているのに、あなたはなぜそうしないのだ」っていう世論の圧力から最終的に死刑になっちゃうわけですけど、なんで皆そうしてるからそうしなきゃいけないんだ、と。思うわけですよ。
ありのままの、なんて言っても許される個性と許されない個性があって、結局は自我の外縁を削り取って売り払わなきゃやってけないんですね、この世の中は。
何はともあれ、不条理文学の金字塔です。
ショーペンハウエル『読書について』
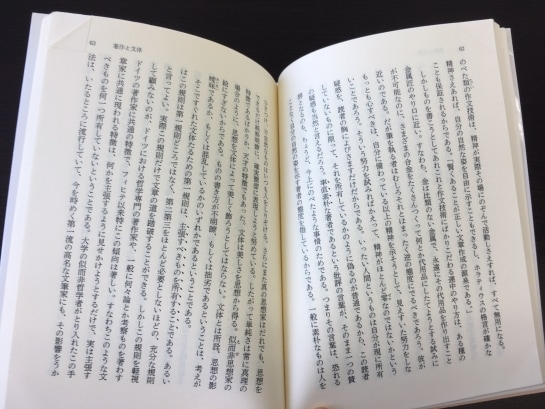
とっつきやすい哲学書、なんてのも評点高し。
タイトルからは想像できないけど「本ばっかり読む奴は馬鹿だ」って内容です。
「読書は、他人にものを考えてもらうことである」
「ほとんど丸一日多読に費やす勤勉な人間は、次第に自分でものを考える力を失っていく」
先生、仰るとおりで。
他人の受け売りだけで偉そうに語る人ほどつまらないものはないですし、本はあくまで思考のエッセンス、ものの見方の一例を提供するものであって、そこから自分はどう考えるか、何を考えるか、ってのが読書の醍醐味だと思います。
で、「人生は限られている、悪書を読む暇はない、だから古典を読め」ってことを強く書かれているのですが、これも完全同意。
やっぱりね、時間はウソをつかないですよ。
活版印刷技術が出来て以来、毎年有象無象の本が飽きることなく出版されていますが、どれも漏れなく時間によって濾過されて、現代までその形を留めたものはやはり骨太で名著揃いです。
ショーペンハウエルは哲学書と言っても単純明快なアフォリズムで満たされているので全然小難しくなく、サクッと読めます。頭がビリビリするね。
本好きなら一度は読んでおきたい本、だと思います。
紹介は以上。
ジョージ・オーウェル『1984年』に出てくる「最高の書物とは読者にわかりきっていることを語ったものだ」っていう言葉が大好きなんですよ。
自分のフィロソフィーを裏付けてくれる本や、自分が感覚的に感じていたことを言語で定義してくれる本ともっともっと出会って、見える世界を広げて、センスのいい回答に使えるストックを増やしていきたいですね。